【その2】 フランス組曲の18の旋律(1)
『フランス組曲』はミヨーがアメリカ疎開中(1940〜1947)、教授の職を得ていたカリフォルニア州オークランドのミルズ・カッレジで作曲されました。1944年に当時の大手出版社のリーズ・ミュージック・コーポレションが「著名な現代作曲家による吹奏楽作品集」の一環としてミヨーに委託したのです。作曲を終え1945年の出版に際してミヨーはプログラムノートに以下のように記しました。
「この組曲は、5つのフランスの地方に因んでいます。5つの地方とは、アメリカおよび連合軍の軍隊がフランスのレジスタンスと共に私の祖国を解放するために戦った戦場のことです。それらはノルマンディー、ブルターニュ、イル・ド・フランス(その中心がパリです)、アルザス・ロレーヌ、そしてプロヴァンス(私の生まれ故郷)です。私はこれらの地方の民謡をいくつか使いました。」(拙訳)
しかしながら、その使われた民謡に関して「どうやって?」、「どれを?」、「どうして?」、「どこに?」についてミヨーは注釈を一切していなかったのです。
実際に5つの各組曲を紐解くと合計18の旋律が使われており、そのうち11の旋律はフランス各地の民謡で、残りの7旋律はミヨーのオリジナルであるということが戦後42年、ミヨーの没(1972)後、15年経った1987年以降、アメリカの音楽家たちの研究で突き止められたのです。研究の経緯や各旋律の解説などについては、1998年に出版されたロバート J. ガロファロ教授による以下の教材に詳しく書かれています。
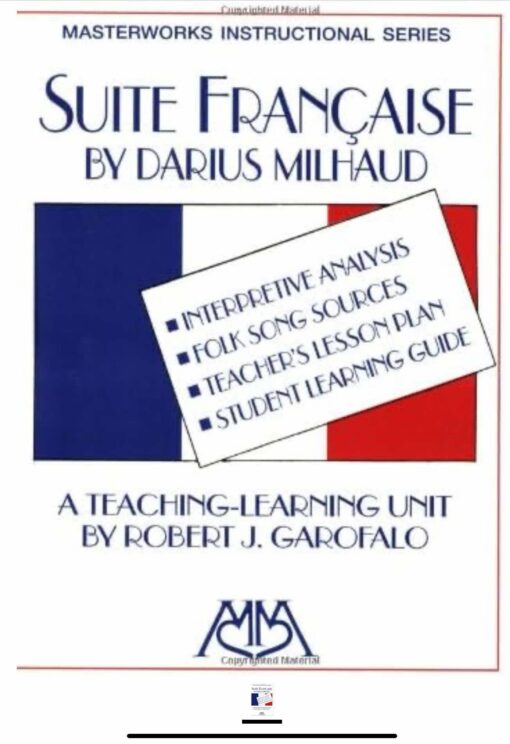
★注目点:民謡の譜面をどうやって入手したか?
そもそもミヨー(ユダヤ人)はナチス・ドイツによる迫害から逃れるために1940年以降アメリカに命辛々疎開していたので、手元にフランス各地の民謡の楽譜を豊富に取り揃えていたとはとても想像できません。ましてや、いくらミヨーほどの天才でもフランス各地の民謡を誦じていたとも考えられません。
実は疎開4年目に出版社からの依頼を受けたミヨーは、マドレーヌ夫人にオークランドの自宅から10キロほどのカリフォルニア州立大学バークレー校の図書館に行かせ、使えそうなフランス民謡のコレクションがあるかどうか探してもらったのでした。
その結果、民族音楽学の先駆者でフランス人のジュリアン・ティエルソが編纂した「Four-four French Folk-Songs and Variants」(1910英仏併記)、及び「Sixty Fork Songs of France」(1915英仏併記)の2冊を借り出したと考えられることが突き止められたのです。この2冊の民謡集から『フランス組曲』に使われている合計18の旋律のうち、ベースとなった10曲のフランス民謡が特定されたのでした。
また、残りの8旋律については、ガロファロ教授が当時86歳でパリにひとり暮らしていたマドレーヌ未亡人に手紙で尋ねた結果、1つは第一次世界大戦前の19世紀末に流行した民謡の旋律で、残り7旋律はミヨーのオリジナルだという結論に達したのです。
マドレーヌ夫人がミヨーのために民謡集を大学の図書館に借りに行ったこと、フランスの古い民謡集が西海岸の大学の図書館に蔵書されていたこと、しかもそれが英語と仏語の併記だったこと、これらのことがずっと後になって突き止められたこと、そしてそれらの民謡をまさに「作曲家の特徴的な作風を保ちながら」組曲にミヨーが組み込んだこと、どれも驚嘆することばかりです。
次回は、「どの民謡が」、「どこに組み込まれているか」についてお話ししたいと思います。
(つづく)
